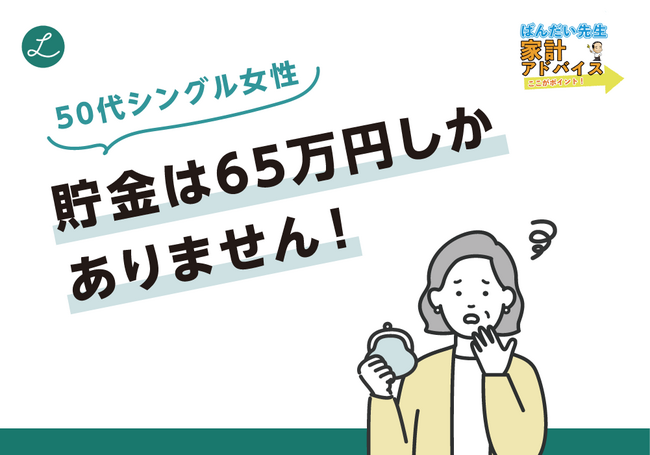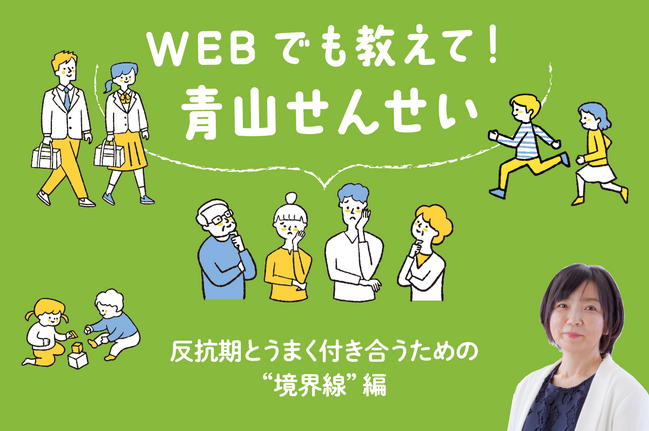教えて!青山せんせい 本当の就学前準備って? 編
2025.09.27

りびえーる本紙でも大きな反響をいただいている子育て応援企画「教えて!青山せんせい」のWEB版。
就学前から10代後半までの子どもたちを持つ親&祖父母へ向けて、毎回さまざまなテーマをお届け。どの世代へ向けたお話も、どこかで必ずあなたのお子さん・お孫さんにつながるのが不思議です。
子どもも親も祖父母も幸せになる…子育てを楽しんじゃうヒントを、この連載で見つけてください!
教えて!青山せんせい 本当の就学前準備って? 編
9月に入ると来年度に小学校入学を控えたお子さんたちの就学準備がいよいよ身近に感じられるようになります。
「うちの子、ひらがながまだ全然読めない!」「みんなに迷惑かけないかな?」
親はできていないところに目が行って焦ってしまうものですが、青山せんせいによると、初めての学校生活を迎える前に身に着けていてほしいもっと重要なことがあるようで…
今回は、就学前の子どもたちに必要な“心の準備”について、考えます。
それでは今回も…教えて!青山せんせい!
本当の就学前準備は“学力”ではなく…
去年のスケジュールを見ていると、このころから小学校入学関係のお問い合わせや講座を多く開催していました。
そうか、もうあと半年もしたら新年度か…って、時間が過ぎるのは早いなと思いました。
で同時に正直に、思うことがあります。
また今年も、学校行き渋りや小学校入学後の不登校で、困って絶望する親御さんがいろいろいろいろ出てくるだろうなって思うのです。
今回は入学までに「〇〇ができないと…」と焦る親へと題して、小学校入学前に本当に大切にしたいことについてお話しします。
入学の声がちらほら聞かれるようになると、多くの親御さんが胸の奥に小さな不安を抱えるものです。
「ひらがなが全部読めないとダメなのでは?」
「計算ができないと困るのでは?」
「ちゃんと座って話を聞けるようになっていないと、先生に迷惑をかけるのでは?」
周りの子と比べたり、入学説明会で配られるプリントを見たりするうちに、「入学までに〇〇ができるようになっていないと…」という気持ちに追われてしまうことがあります。
けれども実際には、小学校の先生方が子どもたちに一番期待しているのは「入学前に学力的な準備を完璧にしておくこと」ではありません。
私が長年不登校のサポートをしていて思うことは、学力的な準備はもちろんですが、むしろ、安心して学校生活を始められる “心と生活の土台” を持っていることが大切ではないかと思うのです。
学校生活をスタートする前に重要な4つのポイント
ではどういったことが大切になってくるのでしょうか。
1. 言葉で気持ちを伝える力
小学校では、先生に頼る場面や友だちとのやり取りが増えます。
「トイレに行きたい」「いやだ」「もう一回やりたい」など、簡単な言葉でも自分の気持ちを伝えられることが大切です。
逆に、字が書けても気持ちを言葉にできなければ、困ったときに助けを求められず、本人が苦しくなってしまいます。
子どもにとって安心して表現できる環境を家庭で整えておくことが、入学準備の第一歩です。

この「伝えること」コミュニケーションができないと、学校が怖い・先生が怖い・不安で仕方がない…つまり、教室が怖くなってしまいます。
大人も同じですが、伝えることができるということは、自分自身が安心できるものです。
「伝えられない」「何を言っているかよくわからない」
「わからないことが聞けない」「よくわからないから不安」
これらは、1年生の不登校の最大の原因だと私は感じています。
だからまずは、伝える力を育てることが大事です。
そして、コミュニケーションと同じくらいに大事なことがあります。それは…
2. 基本的な生活習慣が身に付いているかどうか
「自分の持ち物をリュックに入れる」
「食事を一人で食べる」
「トイレに行ける」
「ハンカチやティッシュをポケットに入れておく」
「自分のことが自分でできる」
これらは特別なことではありませんが、毎日の習慣として積み重ねられていると、学校生活で大きな安心感になります。
入学前に“勉強の先取り”をするよりも、まずは生活リズムを整え、子どもが自分でできることを少しずつ増やしていくことの方が、学校生活のスタートにはずっと役立つのです。
先取り学習をする時間があったら、「自律に向けた関わり」を怒らず叱らずやってください。そして…
3. 失敗しても立ち直る力こそが大切

入学すると、新しい課題や挑戦が次々にやってきます。字を間違える、計算をまちがえる、体操服を忘れる、靴を左右逆に履いてしまう…。
できないことはいっぱいで、毎日できないことであふれるでしょう。
こうした“失敗”を経験したときに、泣き崩れて終わってしまうのではなく、
「もう一度やってみよう」
「次は気をつけよう」
と切り替えられる力が大切です。
「小学校はできないことをできるようになるための場所」だと教えてください。
「できることを学ぶのではなく、できないことを学ぶのが小学校」と親も認知を変える必要があります。
できないことが当たり前で できるようになることが大切なんです。
失敗するのは当然で、練習すれば次第にできるようになるんだと、大人が知っておく必要があります。
この失敗しても立ち直る力は“生きる力”そのものであり、幼児期に小さな失敗を経験しながら、親が「大丈夫だよ」と寄り添ってきた積み重ねによって育まれていきます。そして…
4. 親のまなざしが子どもの安心をつくる
これをもう一度理解してください。
「まだ〇〇ができない」と親が焦るとき、子どもはその視線の中で「できない自分はダメなのかも」と感じてしまいます。
でも親が「ここまでできるようになったね」とできたことを見つめると、子どもは「自分は大丈夫」と安心できます。
この“安心”が、入学後の挑戦する力を後押ししてくれるのです。
入学前の準備は、“〇〇ができるようになっておくこと”よりも、“親が安心して見守る姿勢を持てること”が何より大きなギフトになります。
入学は、子どもにとっても親にとっても大きな節目です。
だからこそ焦りや不安を感じるのは自然なことです。
しかし、小学校の学びは「できない子を置いてきぼりにしない」ように設計されています。
最初は特にゆったりと子どもたちを受け入れようとしています。
だから、子どもの心を安心させてください。
そして親御さんも、おじいちゃんおばあちゃんも、安心してください。
大切なのは、 「完璧に準備された子」になることではなく、安心できる環境と挑戦してみようという気持ちを持っていること」。
そして、その土台をつくるのは、家庭での日々のやり取りと、親のまなざしです。
「大丈夫、あなたはあなたのままで大丈夫」
そう伝えることが、子どもが新しい世界に踏み出すための最高の入学準備になるのです。
子どもたちの、「できない」に温かい光が当たりますように。

「しあわせなおかあさん塾」青山節美さん(松江市)
親学ファシリテーターとして4,000人以上のお母さんたちと接する中で、「親が変われば子どもの未来は変わる」を理念に2018年同塾を開講、講座動員数は現在延べ1万人以上。
登録者数4.43万人(2025年9月末現在)を数えるYouTubeチャンネル「未来へつながるしあわせな子育て塾」でも迷える親たちへ具体的なヒントとエールを送り続けている。