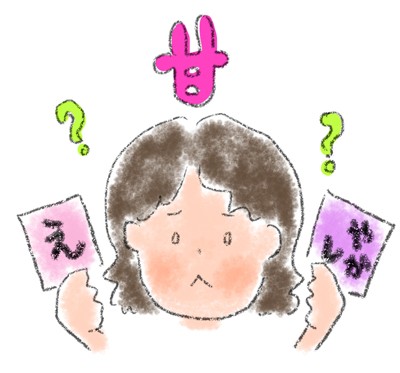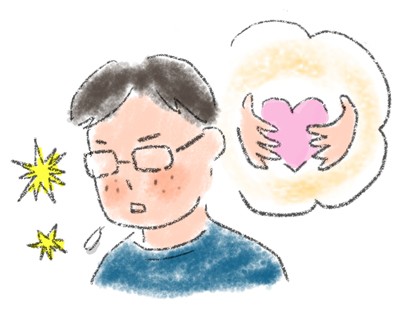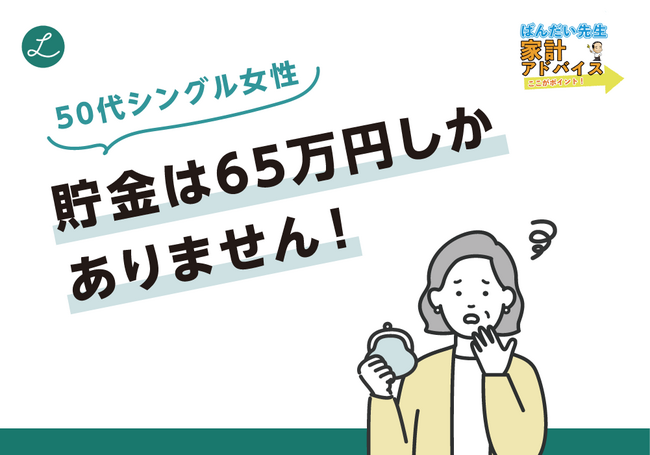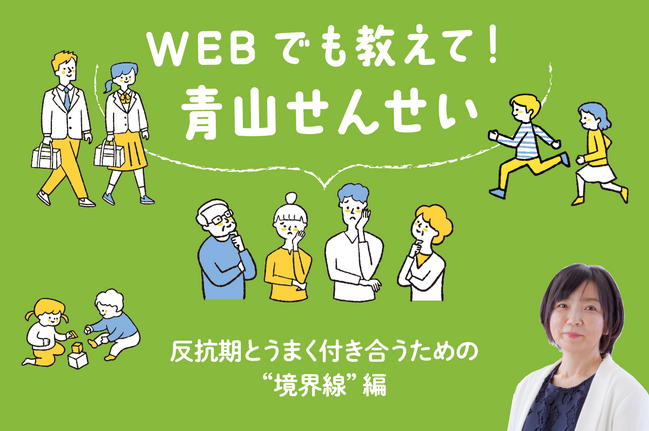WEBでも教えて! 青山せんせい 思春期男子の「甘え」って? 編
2025.07.26

りびえーる本紙でも大きな反響をいただいている子育て応援企画「教えて!青山せんせい」のWEB版。
就学前から10代後半までの子どもたちを持つ親&祖父母へ向けて、毎回さまざまなテーマをお届け。どの世代へ向けたお話も、どこかで必ずあなたのお子さん・お孫さんにつながるのが不思議です。
子どもも親も祖父母も幸せになる…子育てを楽しんじゃうヒントを、この連載で見つけてください!
思春期男子の「甘え」って? 編
幼いころはかわいかったのに…とため息が出る親も多いのが、思春期の男子の態度。
口数がへり、なんだかいつも不機嫌そうで、口を開けば「うざい」なんて言葉はざら。
でもそっけない態度にかくれた“甘え”をちゃんと受け止めることが、のちの自立につながっていくのだそう!
今回は、思春期男子特有の“甘え”の正体と、自立への道筋について考えます。
それでは今回も…教えて!青山せんせい!
気付けていますか? 反抗の裏にある“甘え”
夏休みは、親子にとって特別な時間です。
学校という社会から少し距離を置いて、親と子が一緒に過ごす時間が増えるからこそ、ふだん見えにくかった「子どもの本音」にふと出会うこともあります。
とくに、小学校高学年から中学生くらいの男の子を育てているお母さんたちから、こんな声がよく聞かれます。
「何度言っても起きないんです」
「宿題もせず、ゲームばっかり」
「話しかけても無視…もうどうしたらいいか分からない」
こんな時期に親を悩ませるのが、「甘え」と「甘やかし」の境界線です。
一見反抗的なその態度、もしかして“甘え”かもしれません。
思春期に入った男の子たちは、表情や言葉のうえではとてもそっけなく見えることが多く、その姿に親は戸惑うものです。
しかしそんな姿の奥には、まだまだ「親に見ていてほしい」「自分を分かってほしい」という気持ちがたくさん隠れています。
ただ、その気持ちをうまく表現することができないんです。
思春期の甘えはとても不器用で、わかりづらい…だからこそ親を不安にさせるのです。
たとえば、こちらが何か言うとすぐに「うるせーな」と返してくるようなとき、それは単なる反抗ではないかもしれません。
「自分の気持ちをちょっと聞いてよ」「わかってくれよ」という叫びが、荒い言葉になって出ている可能性があります。
黙って部屋にこもるのも、放っておいてほしいというより「どうせ言っても分かってもらえない」と心を閉ざしているサインかもしれません。
「かまって」と言えないから、わざとムスッとしてみたり、ゲームに逃げ込んで現実をシャットアウトしたりする。
それがこの時期の“甘えの形”なのです。
「甘えさせる」と「甘やかす」の違い
「甘えさせる」ことと、「甘やかす」ことの違いについて 本当によく質問があります。
親が子供の甘えにどう応えるか――これは、この時期とても大切なポイントで、二つの違いを知っておくことは、思春期をうまく超える最善のカギになるかもしれません。
「甘えさせる」というのは、子どもが不安になったときや、ちょっと寄り添ってほしいときに、その気持ちを受け止めてあげること。
話を聞いたり、「どうしたの?」と関心を向けたり、必要なときに寄り添ったりすることです。
思春期の男子でも、ふとした瞬間に近づいてきて、唐突に話し出すことがあります。
「そういえばさ、今日あいつがさ…」などと、ふだんは口数の少ない子が不意にしゃべり出す。
そんなときは、子どもの声にぜひ耳を傾けてみてください。
ほんの数分でも、子どもにとっては“自分を受け止めてもらった”という体験になります。
それに対して「甘やかす」というのは、子どもが本来できることまで先回りしてやってしまうこと。
朝なかなか起きないからと毎日親が声をかけ続けたり、宿題が進まないからとスケジュールを組んであげたりするなど、手を出しすぎてしまう行為です。
また、「やりたくない」と言ったらすぐ代わりにやってあげる、「かわいそうだから」と嫌なことを避けさせてあげる――こうした行動は、親のやさしさが過剰になり、子どもから“考える機会”や“自分で決める責任”を奪ってしまうことにつながります。
長期休みは、生活のリズムが崩れやすくなります。
昼夜逆転などは当たり前で、毎朝なかなか起きない、スマホやゲームの時間が長くなる、勉強は後回し…。
そして親のほうも、「まあ、夏休みだから」とつい手を出しすぎてしまうことも。
ですが、この“ちょっとの甘やかし”が積み重なると、子どもの中に「やらなくても誰かが何とかしてくれる」という依存心が芽生えてしまうのです。
思春期は、自立への助走期間。
ほんの少し手を引けば自分で走れるのに、そのチャンスを奪ってしまってはもったいない。
大切なのは、「放っておく」と「見ていてあげる」の間の wait and see の態度です。
思春期男子との「ちょうどいい距離」とは
思春期の男子が求めているのは、「放っておいてほしいけど、見捨てないでいてほしい」という、とても微妙な距離感です。
何でも口出しされるのはイヤ。
でも何も言われなければ、それはそれで「どうせ俺なんか興味ないんでしょ」と感じてしまう――そんな矛盾した気持ちを抱えているのが、この時期の男の子たちです。
だからこそ親は、「自分でやってごらん」と任せつつも、失敗したときにはちゃんと支え、「ちゃんと見てるよ」という安心感をさりげなく伝えることが大切です。
「宿題やった?」ではなく、「今日はどんなことしたの?」という声かけに変えてみる。
「また寝坊して!」と叱るより、「昨日、ちょっと夜更かしだったかな」と寄り添ってみる。
そうした一言が、男の子たちの“甘えたいけど甘えられない心”をほぐしてくれます。
多くの親子を見ていて思うのは、実は自立のカギは、「ちゃんと甘えられた」経験にあるということです。
不思議なことに、思春期の“甘え”をしっかり受け止められた子ほど、のちのちしっかりと自立していきます。
そんな子をたくさん見てきました。
もちろん最初からうまくいっていなくても大丈夫。
親が気づいたときからでも、甘えを認めてもらい、受け止めてもらえた子は、自立していきます。
自分の気持ちを言ってもいい、受け止めてもらえるという土台があるからこそ、「自分でやってみよう」という意欲が芽生えるのです。
逆に、いつも突き放されてばかりだった子は、自分を信じられず、「どうせ無理」とチャレンジしない大人になってしまうこともあります。
甘えを否定せず、でも依存させすぎない。
その絶妙な関わり方が、この夏、親に求められるスキルなのかもしれません。
反抗期まっただなかの男の子を前にすると、親もつい感情的になってしまうことがあります。
でも、反抗の裏側には、ちゃんと“甘えたい気持ち”がある。
この夏は、そんな気持ちに 向き合ってください。
子どもを変えようとするよりも、まずは親のまなざしを変えてみる。
その一歩が、思春期の親子関係をぐっとラクにしてくれるはずです。
「しあわせなおかあさん塾」青山節美さん(松江市)
親学ファシリテーターとして4,000人以上のお母さんたちと接する中で、「親が変われば子どもの未来は変わる」を理念に2018年同塾を開講、講座動員数は現在延べ1万人以上。
登録者数4.33万人(2025年6月末現在)を数えるYouTubeチャンネル「未来へつながるしあわせな子育て塾」でも迷える親たちへ具体的なヒントとエールを送り続けている。